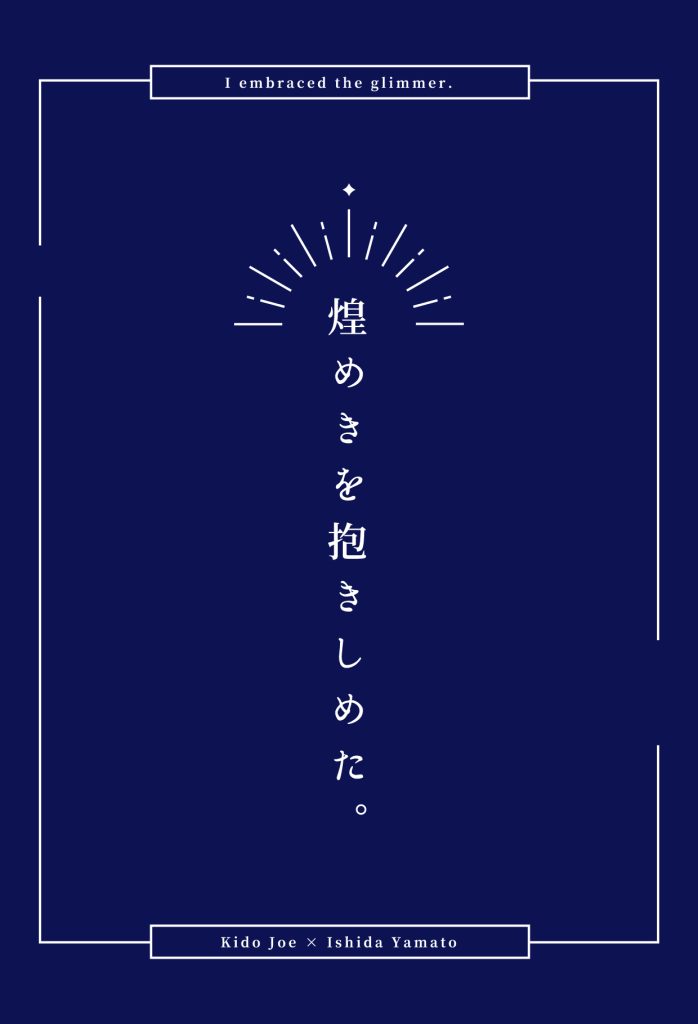
「丈~!こっちこっち!」
「ま、待ってくれよゴマモン!」
二人を気遣ってくれた光子郎達に申し訳なさを感じていたのもつかの間、今の丈はゴマモンが「見せたいものがある」といって走り出したのを必死に追いかけていた。いままですぐに追いつけていたはずの距離が一向に縮まらないのは年齢のせいだろうか。いつも家や大学の中で勉強し続けるのも良くないものだと痛感する。
(にしても、本当に平和だな……)
ゴマモンの後ろを追いかけながらも異変を見つけられるように辺りを見渡していたが、普段と変わりないデジタルワールドにむしろ懐かしさを感じてしまう。ノイズ、というから何かしら音が聞こえたり、歪みが見えたりするのかと思ったが、そういった異常性も一切感じられない。むしろ、静かだと思うぐらいだった。
(——静か?)
ふと足を止める。穏やかな風と木々の擦れる音はいつも通りだ。踏みしめる地面の感触も、視界に映る景色も、おかしな部分など何もない。ここにたどり着くまでに注意深く見てきたのだ。ただ一つ抜け落ちていた欠点としては、丈は最近のデジタルワールドの様子を知らない。だからこそこの違和感に今まで気づけなかったのかもしれない。
(そういえば、ここら辺にデジモンはいないのか……?)
丈達が降り立った地点からはかなり歩いているうえに、そこからさらに別の方向へ丈とゴマモンは進んでいる。かなりの距離を進んでいるはずなのに、その間に誰もデジタルワールドに住むデジモンに出会っていないのだ。単純に丈達が降り立った地点がデジモンが住んでいる場所ではないのかもしれない。だとしてもデジモンどころか何かがいた痕跡すら見当たらないのだ。
丈の中で何か誤魔化してはいけない違和感が芽生えた。前方で丈を呼ぶゴマモンに声をかけて一旦戻るべきか、と考えながらゴマモンを呼ぼうとした時だった。
突然、ポケットに入れていたデジヴァイスが電子音を鳴らして光り始める。
「なんだ……?」
ピコピコ鳴る音は段々加速していき、それと同時に周りの空間がバチバチと電流を走らせて歪んでいった。周囲の風が徐々に強まっていくと丈を吸い込むように吹き荒れ、いつしか竜巻のような渦を描いて足が上手く前へ進まない。
「ッ……⁉︎」
突然現れた正体不明な突風に飛ばされそうになりながらも丈はその場に踏ん張って前を見る。視界の隙間からゴマモンが丈の異変に気付いてこちらに走ってくるのが見えて、丈は思わず叫んだ。
「ゴマモン!来るな!」
丈の言葉が届いたのか。ゴマモンの足が止まったように見えたが分厚い強風の壁のせいで視界も悪く何も聞こえない。その間にも突風で空間が剝がされるように、ところどころに黒い割れ目が現れる。その割れ目からも青い電流が走って、さらに黒い割れ目が増えて周りの空間を歪ませて剥がしていく。ザァーッとホワイトノイズのような耳鳴りに思わず耳を塞ぐが、奥の方で響き続けて激しい頭痛が丈を襲う。
「うッ……!」
ゴマモンは、大丈夫だろうか。巻き、込まれて、ないだろうか。
早く、光子郎、に、言わなきゃ——
朦朧とした意識の中、伸ばした手は虚しく空を切り、そのまま倒れるように丈の意識はプツリと途絶えた。
「あんた……大丈夫か?」
丈の意識が戻った時には、丈はなぜか東京の街の中にいた。耳から入る騒音、視界に映る建物や看板、人通りの多さ。その全てをいきなり五感から感じて脳がパンク寸前な丈を見て、見知らぬおじさんが話しかけてきたのだ。丈からすれば突然東京の街に放り投げられた状態だが、おじさんからすれば街の真ん中で座り込んで固まっている男性がいる状態だ。ジリジリと焼き付けるほどの暑さの中、誰かが街中で座り込んでいたら熱中症といった非常事態を疑われても仕方ない。
「あっ、えっ……と、大丈夫です。すみません」
「本当に大丈夫か……今日は暑いからよぉ、具合が悪いんだったら救急車でも……」
「あっ、いや、本当に!本当に大丈夫ですから」
ポケットから携帯を取り出すおじさんを止めて、丈はその場を逃げるように立ち去った。駆け足で走りながらも混乱した頭で状況を整理していく。
デジタルワールドへ光子郎と調査として訪れたが、その途中で突然現れた空間の歪みのようなものに巻き込まれ、気づいた時には東京の街の中にいた。つまり、あれは突発的なデジタルゲートであり、あの歪みを通して丈は東京に帰ってしまったということだろう。おそらくあの場所はデジタルゲートが不定期に勃発するエリアだからデジタルワールドに住むデジモン達も近づかなかったのだと思えば、あの時誰もいなかった理由も納得できる。状況が理解出来たらまずは誰かに連絡を取らないといけない。光子郎がすでにデジタルワールドに戻っていることを祈りながらスマホを手に取る。
「…………あれ?」
ロック画面に表示されているはずの時刻に八の数字が四つ並んでいた。その時計の下側にある日付も0が八個並んで表示されており、まるでスマホが初期化されたばかりの状態に見えた。デジタルワールドを無理やり行き来したせいでスマホがおかしくなってしまったのだろうか?そう思いながら電話ぐらいは出来ないかと電話アプリを開く。電話帳のデータは辛うじて残っていた。一覧からスワイプする指は焦りと不安で少しだけ震えていた。「光子郎」その三文字に祈りを込めながらタップをして、即座に耳にスマホをくっつける。
『お客様のおかけになった番号は、電波の届かないところにいらっしゃるか、電源が入っていない為かかりません。』
丈の焦り、不安を煽るように、無機質な音声は残酷な事実を淡々と語った。思わずめまいを起こしてしまいそうな体を踏ん張り、もう一度電話を掛け直す。が、何度かけ直しても同じように無機質な音声が流れるだけだった。光子郎がダメならヤマトはどうだろうか。彼はデジタルワールドに行ってないからその影響を受けないはずだ。同じようにヤマトの三文字を押して耳を傾ける。
『お客様のおかけになった番号は、電波の届かないと————』
ダメだ。アナウンスを最後まで聞き終わる事無く電話を切った。日付も時間の表示もおかしくなったということはこのスマホ自体が壊れたのだろうか。突然現れたデジタルゲートの負荷にスマホが耐えられなかった、と思うと根拠や理論は浮かばないが妙に納得は出来る。それは丈の中で「そうであってほしい」という願望なのだろうが、今の丈にはそれが判別できるほどの冷静さを保てなかった。
それならばまだ手段はある。大丈夫だ。スマホが普及して当たり前になったこの現代でもまだ連絡を付ける方法はいくらでもある。
右側の後ろポケットを触ると小さな財布が入っていることが確認できた。普段ならデジタルワールドに落としたら大変なことになると思って持っていかないのだが、今回はたまたま持ってきていたのが不幸中の幸いだった。辺りを見渡して人ごみの隙間から電話ボックスを見つけると、その場から真っすぐ電話ボックスへ向かう。
扉を開けると真夏で締め切られた蒸し暑い空気が丈を気持ち悪く包み込むが、そんなことは気にしていられない。財布から小銭を入れると、繋がる可能性が比較的高いヤマトの電話番号を打ち込んだ。祈るように受話器に耳を当てる。
『おかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになっておかけ直しください』
「……え?」
予想しなかったアナウンスに丈は呆然とした。焦って打ち間違えてしまっただろうか、とスマホを確認しながら打っても同じように無機質な音声が流れるだけだった。
「なにが起きているんだ……?」
スマホから公衆電話に変えてもダメどころか、状況が悪化している。スマホから繋がらないのであれば、スマホが自体が壊れているので済むはずなのに、公衆電話からかけても電話は繋がらなかった。ヤマトとは最近電話したばかりだから、電話番号を変えたとも考えづらい。なのに、どれだけ電話をかけても「使われていない」と受話器から無機質に告げられるばかりだった。
公衆電話の中でもたれかかり、疲労と焦りで頭が回らないながらも少しずつ考えていると、ふと公衆電話の周囲を見た時に黄色の電話帳が置いてあることに気づいた。そして、電話帳の表紙に書かれていた言葉に丈は目を疑い、思わず電話帳を乱暴に手に取ってその文字を見つめる。
「…………二〇〇五年、七月?」
電話帳の右上に大きく白い文字で二〇〇五年と書かれていた。電話帳を更新し忘れているのかと一瞬思ったが、とても五年も放置されていたとは思えないほどの綺麗さだった。
突然現れたデジタルゲート。それを通って出てきた場所は光子郎のオフィスでもない東京の街の中。行き交う人たちのファッションや街並みが今まで見ていた街並みとズレていた違和感。おじさんが持っていた携帯がスマホではなくガラパゴス携帯だったこと。今まで何度もデジタルワールドに行っているはずなのにおかしくなってしまったスマホ。繋がるはずの相手に繋がらない電話。二〇〇五年と書かれた真新しい電話帳。
丈の頭の中で信じたくないが、信じざる負えない事実がいくつもの要素を重ねることで浮上する。
——丈は五年前の東京にタイムスリップをしてしまったのだ。
